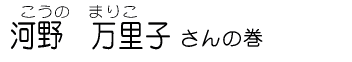  |
|
|||||||||||||||||
1通のダイレクトメールが扉を開く翻訳の勉強をはじめる時の具体的なきっかけ、それは友人の紹介だったり、いまならインターネットでの検索だったりするだろうか。 英語とフランス語の翻訳家、河野万里子さんの場合は、自宅に届いた1通のDM(ダイレクトメール)だった。通信教育「翻訳家養成講座」の案内が送られてきたときに、子どもの頃から漠然とあこがれていた、カタカナで書かれた作者名の下にある翻訳者の名前、今度はそれを具体的にめざそうと思い始めたのだ。 「今思えば、ただの勧誘のDMにすぎなかったのかもしれませんが、あの時の私の気持ちは、ちょうど魔法学校の入学案内を突然手にしたハリー・ポッターさながら!(笑)でもそれで、私の場合はほんとうに道がひらけてしまったのですから、人の運命って不思議ですよね」 「海外の絵本や児童書が大好きだった私は、子どもの頃からカタカナで書かれた著者名の下に、漢字の訳者名があるのをうっとり(笑)、じっと見つめていて、『こんなお仕事あるんだなぁ。いいなぁ』と思っていました。それはピアノを始めても、やめても、学生になっても、会社勤めをするようになっても、結婚してからも、変わることのないあこがれ――今ではなんだか気恥ずかしいことばですが――だったんです。ただ、きっかけや、その道への入り口のようなものが、ずうっと見つからないままでした。それが、会社も退職し、結婚もして、さてこれからどうしようかな、という時に案内が送られてきたんです。まさに具体的なきっかけになったというわけです」 ピアノの道から語学の道への方向転換3歳の頃にピアノを始めた河野さん。それから19歳まではピアノを弾くことが生きることの中心にあったという。もちろん、その時に目指していたのはピアニスト。10歳の時にはオーディションを受けて、高名なピアニストである芸大教授の教室に入り、毎日毎日ピアノを弾いていた。練習も好きだった。ただ、ピアノの世界ではなぜかいつも結果が出ず、最終的にそこから離れる道を選んだ。ピアノをやめたあとは、方向を変えて語学の道へ。大学の外国語学部に進学し、サークル活動ではテニスを楽しんだ。そして卒業後の進路は、堅実なメーカーへの就職を選ぶ。 「会社には、まる3年いました。希望どおり、仕事の上で英語もフランス語も使う機会があり、海外からのお客さまもあって、活気のある楽しい部署でした。大卒女子の先輩や同期もたくさんいて、現在にまでつながるような『仕事というものの基礎』を、しっかりと身につけさせてもらったと思います。これにはとても感謝しています」 結婚と同時に、夫となった人の留学先だったアメリカに行くことを選び、退職したが、この渡米が、子どもの頃から就きたいと思っていた仕事への流れを作ってくれたと河野さんは言う。退職する決断をしたときは寂しかったが、だからこそ人生の転機はおもしろいものだと感じているそうだ。 翻訳家の道へDMの誘いにのってはじめた通信教育で学ぶうち、河野さんはどんどん翻訳のおもしろさにめざめていく。そして、雑誌『翻訳の世界(当時)』第13回翻訳奨励賞で最優秀賞を受賞。授賞式で出会った新潮社の編集者の方に声をかけてもらったことが縁で、フランソワーズ・サガンの翻訳をすることにもなった。ちょうどその頃、河野さんは男の子を出産した。 「出産は、サガンでの本格的なデビューとほとんど同時になりました。息子が生まれたのが8月、サガンが出たのが9月。産後すぐに目を使うとよくないと言われたので一か月だけ休みましたが、その後すぐ仕事に戻り、実家の母に多少子どもを見てもらいながら、やりかけていた次の翻訳を仕上げました。あの時は死にそ~でした(笑)。 子どもは1歳になってから保育園にお願いしたのですが、我が強くて私とは違うタイプの子だったので、毎日が戦い(!?)みたいな日々でした(笑)。楽しかったりかわいかったりといったこともたくさんありましたが、当時は、それ以上に早く仕事に集中したくてたまらなかった」 ところが15年たったいまでは、戦ってきた成果なのか、息子さんとはツーカーの仲という。なにかと話や感覚が合うだけでなく、ピアノも弾くという息子さん。かつて河野さんが弾いたピアノを、今度は息子さんが使っている。 「子どもが生まれてからは、絵本や児童書、ヤングアダルトの仕事もするようになりました。もともと好きな分野だったので、大歓迎。それに私、息子が10歳になる頃まで(つまりひとりで本が読めるようになっても)毎晩読み聞かせをしていたんです。私にとっても、いい勉強と蓄積になった気がします」 最近のお仕事から仕事は家族を送り出したあと、だいたい9時から5時までの間にすることにしている河野さん。最近、翻訳した本について話していただいた。 「白水社から刊行された『キュリー夫人伝』(エーヴ・キュリー著)は、新訳でいまの時代に読みやすいものをということで、70年ぶりに新訳にしたものです。偉大な人の全生涯の物語を訳すというのは、経験したことのない不思議な心地になることがいろいろありました。彼女の運命や生涯はすべてもうわかっているのに、私が日本語にすることによって、もう一度目の前でその人生が進んでいくような。だから私がサボると、彼女の運命も、止まっている(笑)。彼女の人生という一冊の書物が天にあって、私がそれをつかさどる神様になったみたいな感覚がありましたね。そうして、いま生きている私たちひとりひとりにも、実は全生涯の書かれた本が、すでに天にあるのではないか、なんて思ったりして」 2006年3月に刊行された『キュリー夫人伝』の表紙の色には深紅が選ばれた。深紅はキュリー夫人の情熱をあらわし、それでいて控えめな性質をも伝えるかのように、薄い半透明のカバーがほどこされるという、美しい造りの伝記本になっている。1938年の刊行以来読み継がれ、その後何度かの改訳を経て、今回の全面新訳となった一書である。偶然にも3月末には、もう1冊、古典として名高い『星の王子さま』も新潮文庫から新訳として刊行された。 「『星の王子さま』はずっと新しい日本語にしたいと思っていた本なんです。私ならこんな風に訳したい、こんな文章で伝えたいと思い続けていた本なので、手がけることができてとてもうれしかったです」 旧訳のあるものを新たに訳すことにも、とりたててプレッシャーを感じることはないという。 「私は実は引っ込み思案なところがあって、翻訳の勉強も通学より通信教育を選んだほど。ピアノを弾いていた時も、ふだんのレッスンはよくても、ここ一番で力が出せないことが多かった。でも、ことばの世界では全然違うんです。この仕事では、「ここ一番」で、自分としておそらく100%近く力が出せる。プレッシャーより、うれしさやおもしろさ、わくわく感のほうが強いんです」 河野さんがみずみずしく新訳された『星の王子さま』(新潮文庫)は、劇団ひまわりがミュージカル化したものの底本となった。ミュージカルは、2006年8月には九州、大阪で、9月には名古屋で上演され好評を博した。2006年10月18日〜20日(札幌市教育文化会館小ホール)、東京では来春2007年3月20日から4月にかけて予定されている。お近くの方はぜひ足を運んでみてはどうだろう。 河野さんの文章は翻訳とともに、あとがきの読みごたえにも定評がある。数年前に雑誌で連載していたエッセイは、新しい号が出るのが待ち遠しいほどだった。どこかでまたエッセイを連載して、読者を楽しませてほしい。
インタビュアー:林さかな(2006年9月) |
