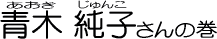  |
|
|||||||||||||||||
青木純子さんのインタビューは、阿吽の呼吸でお仕事をされている東京創元社の編集者、井垣真理さんにも同席いただいた。隣同士に座ってふたりでニコニコと受け答えしている姿からは、まるで姉妹のような空気を感じる。 おふたりが最初にお仕事したきっかけはどういうものだったのかをうかがってみると、そこにはなんとも驚くエピソードがあった。 一足飛びにその話をしたいところだが、まずは翻訳の師匠との出会いから紹介していこう。 師匠との出会い「私の師匠は工藤幸雄先生です。 苦労して下訳したシンガーの3冊の本、『やぎと少年』(ここには旧姓の井沢純子さんで)、『よろこびの日 ワルシャワの少年時代』『まぬけなワルシャワ旅行』(いずれも岩波書店)の訳者あとがきには、青木さんのお名前もしっかり紹介されている。 大学院進学工藤幸雄さんを通して知ったシンガーは青木さんを魅了し、もっとしっかり文学を勉強したいという意欲にかりたてた。そこでどうしたか。すでに結婚もしていた29歳の青木さんは早稲田大学大学院に入学し、系統だって文学を学び始めたのだ。大学院では修士から博士まで通算7年在籍した。その院生時代に翻訳家としてのデビューもはたしている。「大学院に入って1年目くらいの時に、工藤先生から新潮社の編集者の方を紹介していただき、1冊やってみないかということで『こころの扉をたたいた猫たち』(サマンサ・ムーニー著)を訳しました。先生の所で勉強しはじめて8年目でした」 「大学院に在籍していた時はこの1冊以外、翻訳の仕事はせず、勉強に専念しました。なんて言うとかっこよすぎるけど、映画にどっぷりはまったのもこの時期かな。もともと、将来の仕事として翻訳をやるために大学院に行ったわけではないんです。シンガーという作家に出会い、文学の魅力にめざめた時、もっといろいろなことを知りたくなったんですね。大学の4年間も英文学科でしたが、どちらかというと言語学のほうに興味があったし、それほど小説を読んだわけでもなく、まだまだ勉強が足りないと思っていました。ですから院に進もうとしたのは、純粋に好奇心でしょうかね、文学に対しての。シンガーの作品の魅力はとても大きかったというのもあると思います。修士論文はもちろんシンガーでした」 編集者、井垣真理さんとの出会い「そして大学院を出た頃、東京創元社の井垣さんと出会ったんです。これまた工藤先生つながりなんですよ。この頃、先生は東京創元社でミロラド・パヴィチの『ハザール事典―夢の狩人たちの物語 男性版・女性版』を翻訳出版したばかりで、編集担当の井垣さんがさらに別のパヴィチ作品『風の裏側』を先生に預けて翻訳をお願いしていたんです。そして先生のご自宅で忘年会か何かあったときに、井垣さんとはじめてお会いしたんです。そこで先生がいきなり井垣さんに「あれ(『風の裏側』)、純子ちゃんに頼んだからね」って(笑)」 ここで井垣さんに登場してもらおう。 「いやあ、びっくりしました。お願いしていた翻訳をこちらにひとこともなく、『もうお願いしたから』って。『純子ちゃんて誰? 何者?』と、お会いしたこともないんですから、本当にびっくりしましたし、ショックでもありました。お願いした方と違う方になったわけですから。断るに断れないし。実力のほども知らないのにどうなるんだろうって。それこそ『ガーン!』って感じでした」 実は、この話、当のご本人である青木さんもその日、初めて聞く話だったという。 「ええ、事前に何も聞いていなかったんですが、やらせていただけるならって。私って積極的な人間じゃなくて、みなさんに後押ししていただいて進んでいくタイプなんですよね。もちろんやるからにはきちんとしたものをと思いましたし、すぐにセルビア語英語辞典を買いこみ、ユーゴスラビアの歴史もスピード学習(笑)。私って調べ魔なんです」 こうして『風の裏側』が刊行された。ちょっとマニアックな内容の小説で読者を選ぶものでもあったが、書評でも多くとりあげられ、東京創元社での初仕事は好スタートをきった。 ところで、井垣さんは青木さんに会って一緒に仕事をしているうちに、何やら天のお告げでもあったらしく、たまたま届いた高校の同窓会名簿をパラパラ繰っている時に、「なんだかどこかでお会いしているような気がしているけど、ひょっとしてこの名簿にあったりして……なーんちゃって」と探してみると、これがビックリ、ドンピシャリ。なんと青木さんは後輩だったのだ。ただし、井垣さんが卒業して青木さんが入学しているので、会っているわけではないのでしたが。 青木さんの仕事をみていて、実力に信頼を寄せた井垣さん、きっかけは思いもよらないものだったが、同窓とも知り、以降は、これぞと思う作品を青木さんに依頼するようになっていった。 こうして青木さんは院を卒業してからは非常勤講師として複数の大学で働くとともに、翻訳業を夏休み、冬休みなどまとまった休みでこなし、二足のわらじ生活をおくるようになる。 翻訳の仕事は私の主食?「言葉をこねくりまわすのがすごく好き。いつまででも言葉と戯れていたい。訳すスピードはめちゃくちゃ速いけれど、推敲でスローダウン、ゲラも3校くらいまでいつも真っ赤にしてしまって、井垣さんの顔を毎回ひきつらせてます(笑)。それと翻訳に関して、私には優秀なブレーンもいるんです。もう20年以上のおつきあいになるアメリカ人で、彼女は文学がとても読める方なので、原書のニュアンスや英語表現の背景にある文化など、いつも的確に教えてくれて助かっています」 ここ5年ほどは、家族の介護で非常勤講師の仕事はやめて、在宅でできる翻訳の仕事だけをしている青木さん。井垣さんは、青木さんの仕事の集中力はすごいんですよと教えてくれた。 「彼女の集中力は本当にすごい。朝から夜中まで仕事部屋に入ったら、食事を忘れてずっと翻訳をしているらしい。これは食い意地のはった私には信じがたいことです」 え! ごはんも食べずに!? 青木さんはニコニコしながら、 「だっておなかがすかないんだもん。夜中に区切りをつけてごはんを食べるだけで十分。食べてるのは言葉だけなのに、なんで太るのかなあ。辞書に囲まれ、日本語と一人遊びしているって感じでしょうかね。もちろん、突発性失語症にかかって、ぴたっと来る訳語が出そうで出ない、なんてことはしょっちゅうですよ。そんな時は日本の笑える小説を読んだり、編み物をして気分転換。もちろんアメリカの友人や井垣さんも心強い味方です」 仕事の参考にとよく観ているのは、「アクターズ・スタジオ・インタビュー」(BS放送)だという。 「役者さんの仕事は翻訳に通じるものがあるように思えます。作品の声を聞き、役作りをしていくところなどは特に。翻訳者は俳優になりすぎてはいけないけれど、作品の声をよく聞き、黒子としてひきたてるところは常に意識しています」 青木純子訳の本は少しクセの強い作品が多いけれど、読者を裏切らないおもしろさがある。訳している本は井垣さんとのコンビ本が圧倒的多数。そこで井垣さんに、どんな風に原書を探されているのか聞いてみた。 「もうひたすら私の好みが基本です。私の変なアンテナにひっかかったものです。それからフランスの書評誌紙を読んでいて仏訳された英米その他の作品に出会うことがありますがそこから選んだりもしています。ただ、フランス人の好みと日本人のそれが必ずしも近くないので、それはやはり自分のアンテナに頼ります。そしてよしコレだ! と思った本を青木さんにお願いしているんです」 なるほど。英語のみならずフランス語が堪能な井垣さんならではの選書。ここから読者を新鮮に楽しませてくれる本が刊行されているのだ。 お互いがプロの仕事を支え合っている絆は本当に強い。これからもおもしろい! と唸らせてくれる本の刊行を一読者として楽しみにしている。 インタビュアー:林さかな(2009年9月) |
