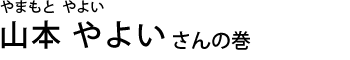  |
| |||||||||||||||||
翻訳家以前──迷うことなく英語の道へ「当時は女の子の進学先は文学部、そういう公式があったんですよ」 こたつの向こう側で、山本さんは高校時代をそう振り返る。 山本やよいさんを訪ねたのは、前日の大雪がいたる所に名残を見せる日だった。見晴らしのいいマンションに案内されると、廊下の一角には小ぶりの花器に千日紅がアレンジされ、ベランダにはゼラニウムを始めとする色鮮やかな花が並び、外の寒さを忘れさせてくれる華があった。 団塊の世代ですから、と話は続く。当時は法学部や経済学部に入ると何百人の男子の中に、女子はわずか1、2名だった。女子が進学するのなら、文学部が当たり前。中には、大学進学を花嫁道具のひとつと捉えている家庭もあった。山本さんは英語を使った仕事がしたい、そんな想いを抱いて同志社大学の英文科に進んだが、文学部以外で英語を勉強するという選択肢は頭になかった。周囲も自分も疑問を感じずに進んだ道だった。 「でも、惜しかったかな。法学部に行っておけば、相当もてたらしいです」 英会話ができるようになりたいとESSに所属、英語にもまれる学生生活を経て、卒業後は故郷の福井で英語教師となる。勤務先は共学の高校だった。新卒で生徒とあまり歳が違わないこともあり、センセイではなく、「やよいちゃーん」コールを受ける毎日。和気あいあいとした場面が思い浮かぶが、楽しい反面、悩みもあった。 「教師として、自分がどれだけ生徒の学力を伸ばすために役立っているのか、そこがつかめなくて悶々としていました。生徒の伸び具合は、すぐに目に見えるわけじゃないでしょう。たまに目立って伸びる子がいると喜び、できない子がいれば落ち込んで。わたしにはむいてないなあと、つくづく思いましたね」 高校教師でいることに疲れてしまい、高校は2年で退職した。しかし、当時の教え子とは今でも交流があるという。 翻訳家への扉──出逢いを重ねて退職後は家庭教師をするかたわら、できたばかりの翻訳学校の通信教育を受講した。しかし、課題は最後まで出せずに挫折。そんな山本さんが本気でやってみようと思ったきっかけは、結婚した相手の言葉だった。 「女性も自分の世界を持とう、そう言われたんです。家にこもっていないで、外に目を向け没頭できるものを見つけろと。そのかわり、食事の支度ができなくて店屋物になっても、1度も文句は言われませんでした。数年前に亡くなりましたが、本人は完璧なリベラリストだと自負していましたし、実際にそうだったと思います」 結婚を機に関東に住まいを移していた山本さんは、くだんの翻訳学校が通学部を始めたことを知り、本格的に勉強することを決意。そしてこの通学が、結果的にプロとしての足がかりとなる。 まず、半年しか開講されなかった、幻のと言われる小泉喜美子氏のクラスを受講した。授業が終わればカラオケに繰り出すこともある楽しいクラスだった。弟子は取らない、下訳は使わないという小泉氏だったが、講座の最後に早川書房の『ミステリマガジン』に紹介してくれることになった。当時、青木雨彦氏が一般読者にインタビューする「街角のあなた」というコーナーがあり、そこに出るよう推薦されたのだ。そのインタビューに同行した編集者に、今度何か訳したら見せてごらんなさいと言われる。 「社交辞令だとは思ったのですが。でも2年ほどしてからでしょうか、本当に短篇を訳して持ち込みました。雑誌で読んでおもしろかったドナルド・E・ウェストレイクのドートマンダーものです」 持ち込んだ短篇は残念ながら採用にならなかったが、その頃の山本さんは中田耕治氏のクラスを受講する一方、校内のオーディションに合格し、清水俊二氏の下訳をした経験があった。内容はサミー・デイビス・Jrの自叙伝で、銀座の裏通りにある映倫で委員をしていた清水氏のもとへ4カ月間、毎週通い詰めて教えを受けた。 「毎週決まった分量を訳して持参しました。そうすると、びっちり朱が入った前回の原稿を戻してくださるんです。それを毎週ですものね。下訳というより、個人レッスンを受けていたようなものでした。基礎的なことは、この時期にたたき込まれました」 そうした経験を見込まれ、持ち込みから1、2カ月で『ミステリマガジン』より短篇の翻訳を依頼される。こうして、ジャック・リッチー「カメリアの香り」で初めて翻訳家、山本やよいの名前が出た。81年のことだ。それからは、同誌で継続的に短篇をこなし、それと平行して、クラシック・ミステリファンには嬉しい作品、エラリー・クイーン編の短篇集を共訳で出すことが決まる。初の訳書なので、ゆっくり、安心して取り組めるものをという配慮だった。 しかし、何が起こるかわからないものだ。突然、急ぎの仕事が舞い込んだ。『アニー』の映画公開にあわせ、ノベライズを1カ月半で訳すよう依頼されたのだ。 「初めての仕事でそれはないだろうと(笑)。今思えば、英語も簡単でそれほど厚い本でもなかったのですが、とにかく初めてですから、大変でした。クイーンは延期してもらい、朝から晩までかかりきりです。納品したら5キロ痩せていました。でも、長篇初仕事から修羅場をくぐって、もう何が来てもこわくないと思えるようになりました。編集者さんのあいだで噂になったようです。あの子は丈夫だから、酷使しても平気だって」 続いて、念願のミステリ長篇の依頼がきた。憧れのポケミスだった。しかし―― 「順調なあまり気の緩みが出ていたんでしょうね。思い入れたっぷりに訳したら、原文から離れすぎている、2カ月あげますから全部直して下さいと原稿を突き返されたんです。ここで踏ん張らなかったら、翻訳家生命が終わると必死で訳しました」 またもや修羅場だったが、その甲斐あって原稿は無事受けとられた。作者の世界と訳者の世界の重なり具合について改めて考えさせられ、いい教訓になった。 翻訳家の仕事──調教の苦労と読者的な愉しみ山本さんはその後、サラ・パレツキー、ピーター・ラヴゼイなどの人気ミステリ作家たちと出逢う。 「パレツキーの原文はとてもパワフルです。翻訳の作業では、原文に圧倒されそうになるのを、騙し騙し手なずけて、おとなしくさせる。だから1冊終えるとぐったりします。1作目からそうでしたし、それは今でも変わりません」 『サマータイム・ブルース』で女性探偵小説ブームの火付け役となったパレツキーは、強く、そして情にもろい主人公V・I・ウォーショースキー(ヴィク)の活躍を通じ、企業犯罪の裏に存在する女性、老人、移民など社会的弱者に対する横暴について、一貫して問題提起を続けてきた。新作『ハード・タイム』でヴィクは40歳を過ぎたが、相変わらず文字通り体当たりで事件の調査に取り組み、怪我が絶えない。気づくと病院のベッドの上で、そこには山本さんお気に入りのキャラクターである、医師ロティの心配そうな顔がある――とおなじみの状況で読者をやきもきさせるヴィク。しかし、現実の世界ではシリーズ開始から20年近くの歳月が流れ、女性を取り巻く環境もだいぶ変化したと思われるが、まだヴィクは闘わねばならないのだろうか。 「パレツキーに言わせると、女性作家の発言権は向上しているけれど、その一方で女性に対する圧力は大きくなっていると。彼女にとって、作品は自分のメッセージを発信する手段。社会に働きかけたいという気持ちが強いんですね。そういう意味では作家というより、社会運動家としての側面が強いかもしれません」 作品の内容だけでなく、女性作家の集まり《シスターズ・イン・クライム》の創設などを考えれば、なるほど、パレツキーの意識の高さが伺える。そんな作家の原文がパワフルだという言葉に納得がいった。 「でも、新聞記者のマリ・ライアスンや、コントレーラスおじいさんのように、ほっとするような登場人物もちゃんといるんですよね。そうそう、このシリーズの翻訳は大変ですが、ゴールデン・レトリバーのペピーが登場してから、さらにほっと一息つけるようになりました」 カウンターには、いま実家に預けてあるというプードル、ジュッピーの写真が飾られていた。 「いま一番楽しいのは、ラヴゼイを訳しているときです。波長があっているのかな、するすると訳文が出てきます」 良質の歴史ミステリを書き続けてきたラヴゼイが、初めて現代を舞台にして書いたシリーズが、『猟犬クラブ』などで知られるバースのダイヤモンド警視シリーズだ。人情味あふれる愛妻家の熱血警視が、古色豊かなバースの街を行く本格ミステリ&警察小説は、発表されるやいなや人気を博した。山本さんは数冊の歴史ミステリに続き、このシリーズをメインで訳している。ラヴゼイの英文は、読んで楽しく、訳しても楽しく、自然に受け入れられるのだという。 「新作のリーディングの依頼があると、待ってましたとばかりに、わくわくしながら取り組みます。ああ、今はわたしひとりの物だと喜びにひたって読むんです。翻訳家になってよかったと思う瞬間ですね」 翻訳家の食卓──ワインとみじん切りの効用山本さんと言えばミステリ、そしてワインだ。 「10年ほど前でしたか、弁護士でワイン研究家の山本博さんが、訳したい本があるけれど時間がなくて無理なので、誰かいないかと探していらして。そこでわたしが訳すことになったんです」 以前からお酒はたしなんではいたが、当時、ワインに関する知識はほとんどなかった。そこで、ワイン関係の本を訳すにあたっては、かなり勉強をした。銀座のワイン・バーに出かけては、飲みながら知識を仕入れた。飲みながら、だったので、どこまで記憶に留まったかは定かではない。しかし、ご趣味はと訊かれれば、にっこりして「飲み食い」と答えるほど、もとより食には興味津々だから、ワインの世界にはのめり込んだ。この仕事が縁となり、鎌倉書房から出ていた酒の専門誌『乾杯』で関連記事の翻訳を担当したこともある。翻訳をするジャンルには基本的にこだわらない。ただ、食関係の本は、また訳したいと思っている。 「贅沢という意味ではなく、母が食にこだわる人だったので、その影響かもしれません。家でもまめに作っていましたし、外食をして美味しいものがあれば、すかさずレシピを訊いていましたね。はい、わたしも料理は好きですよ。レパートリーは、ごく普通の和食が多いです。お総菜ね。ダダッと野菜を刻んでいる最中に、つかえていた部分の訳が浮かぶこともあるから、いい気分転換になっています。女性は家事があるから大変だろうと言う人もいますが、ずっと机に向かい煮詰まっているのはかえって良くないですね」 翻訳家の交流──信用第一山本さんは現在パレツキー、ラヴゼイの他にも、メアリ・ジェーン・クラーク、チャールズ・トッドなどレギュラーの作家を多数抱えている。仕事の進み具合を、積み上げた原稿用紙の高さでたしかめた頃から、パソコンのファイルの容量でたしかめるようになった現在まで、ひっきりなしに仕事のオファーがある。 「でも1度だけ、仕事のストックがなくなり慌てたこともあったかな(笑)。翻訳家は訳さないと生活できない。何の保証もない厳しい世界です。信頼関係を築くことは大事ですよ。そういう意味でも、締め切りは守ります。まず最初に、締め切りよりも早めに終わるよう1日あたりのノルマを決め、訳し始めるんです。最後のほうは、どういうわけか随分ずれてくるのですが、ラストスパートをかけて納品です。急ぎでも山本に頼めば、きちんとあげてくる。そういう信用はいただいていると思います」 週末ぐらいはオフにしようと思いながら、家にいるとつい仕事をしてしまう。朝型人間で、昼間は仕事、たまに電話でおしゃべりし、メールのやりとりに走って逃避、週に1度は近くのジムに通い、深夜過ぎには休む。友人たちと遊びに行くことが楽しみだ。しっかり休暇を取るときは、好きな旅行に出る。原作者たちに会おうとシカゴやバースまで訪ねていったことや、アメリカで催されるミステリ大会のバウチャーコンに数年続けて出席したこともある。今年はワイナリー巡りの案が出て、盛り上がっているところだという。 年に1度、友人たちと集い、おおいに話す機会が訪れる。ミステリ翻訳家と編集者の忘年会だ。昨年で15回を数えたこの忘年会、最初は出版社の主催で始まったが、スペースの都合により数年で中止されることになり、同業者の交流を図るせっかくのチャンスをなくすのはもったいないと、山本さんは長野きよみさんと共に幹事役をかって出た。その後は自主的に忘年会を催し、参加者は年々増えて、いまでは200名以上が集う大きな会となっている。 その人数では、幹事はさぞかし大変ではないだろうか―― 「幹事なんて大役をやるつもりはなかったのに、気づけばそうなっていたんです。50人が80人になり、100人を超えたときはどうしようかと思いましたよ。それが今では200人。たっぷり話ができそうでしょう。でも、去年、幹事役を後輩にバトンタッチするまでは、1次会で室内に入ったことはほとんどなかったんです。そう、幹事はずっと入り口の受付にいるものだったんですねえ」 ふとベランダへ目をやると、外はすっかり暗くなり、遠くに街のシンボル・タワーが光っていた。話がベランダに並んだ花におよぶと、花は好きですが枯らします、毎年どっと買い足してくるの、と教えてくれた。細やかで豪快で。その話しぶりがまたごく自然だった。 注目作を訳し続け、外から見れば華やかに映る人気翻訳家。夢はベストセラーをあてて隠居し、暖かい所へ移住することだと笑う山本さんは、堅実に仕事をこなし、人との交流を大切にしている自然体の女性だ。 「わたしはこつこつ訳している、それだけなんですよ」 その言葉が清々しかった。 インタビュアー:三角和代(2001/1/28) |
