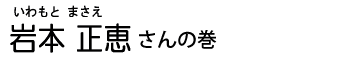  |
|
|||||||||||||||||
|
岩本正恵さん。硬軟とりまぜた訳業ながら、そのたしかな仕事ぶりにファンも多い。岩本さんのこれまでと、日常、そしてこれからについてお話をうかがった。 きっかけはヴォネガット「大学の専攻は英語ですが、東京外大を選んだのは、二次試験の入試科目が少なかったからという、ただそれだけの理由です。ここなら、英語と現代国語さえできればなんとかなる、と」 東京外国語大学に入学した岩本さん。それまで本は好きで読んでいたものの、とくにアメリカ文学に興味があってはいったわけではないという。当時の東京外大の英米語学科には、志村正雄さんや佐藤良明さんなど、アメリカ文学の教授陣が揃っていた。 「英語専攻なんだから、ペーパーバックぐらい読めるようになりたいと、新宿の紀伊國屋で最初に買った一冊が、たまたまカート・ヴォネガットだったんですね。読んでみて、こんな世界があるんだって、新鮮な驚きを受けたんです。いま思えば、そのときの出会いが、わたしが翻訳の仕事をするようになる最初のきっかけだったのかもしれません」 会社員から翻訳者へ大学卒業後は、ごく普通に一般企業に就職。会社生活はそれなりに充実していたものの、自分ではあまり会社員には向いていないと感じていた。そんなときに知人の依頼で雑誌のエッセイを訳したところしっくりきて、そこから翻訳を将来の仕事として考えはじめたという。結婚したのちに会社員を続けつつ翻訳学校へ通った。 「『フィールド&ストリーム』というアウトドア雑誌のエッセイを何回か訳しました。それから翻訳学校の紹介で、終戦後50年の節目で出た『原爆投下決定の内幕』の共訳に参加させてもらったんです。『毒殺百科』や『絞首刑執行人の日記』という実録犯罪ものを訳したのもこのころです。それに急ぎの下訳もしました。当時はまだインターネットが普及してなかったので、原稿のやりとりそのものが原始的で、郵便物を回収にくる最後の便に間に合うように、ポストまで毎日走ったんですよ。いま思えばいい経験ですね。そのころメールがあれば、また全然違っていたでしょうね」 岩本さんは、古くからのMacユーザーでもある。当時は出力した紙とデータを収めたフロッピーを郵送していた。 「パソコンは仕事で毎日使っています。でも自宅でひとりで仕事をしていると、なんだか浦島太郎になるんですよ。世間の常識の進みかたから取り残されてしまうというか。えっ、いつのまにフロッピー入稿じゃなくなったの? いつのまにメールに原稿を添付するときは、テキストファイルじゃなくてワードのドキュメントってことになったの? って感じです。わたしはMacユーザーだからワードは使わないんです、なんて言いわけは、くやしいけどとっくに通用しないですよね」 また、音楽関係の翻訳書を数多く手がけているが、ご本人の趣味でもあるのだろうか。 「音楽は好きですが、ごく普通のレベルです。それでも『エレベーター・ミュージック BGMの歴史』のときには、必要なCDをかなり買いまくりました。いまでもイージーリスニングについては、ちょっと詳しいですよ。どこかに出かけると、つい耳を澄ませて観察してしまいますね」 当時はネット上での試聴というシステムもなかったため資料さがしには苦労が多かった。こうして仕事を通じて広がる世界が、ご自身にも深くしみ通っていくようだ。 「それまでラップ/ヒップホップは、たんにリズムとノリの音楽ととらえていたのですが、『ラップという現象』を訳してからは、曲の背景や流れもわかるようになったので、別の楽しみかたができるようになりましたね」 『翻訳夜話』のこと岩本さんは、村上春樹さん、柴田元幸さんによる『翻訳夜話』(文春新書、2000年)に、若い翻訳者として登場している。ほかの若手翻訳者は柴田さんの教え子などだが、岩本さんの場合は、幸運な偶然だった。 「『翻訳夜話』のフォーラムで、柴田さん、村上さんのお話をじかにうかがえたのは、とても刺激的でした。当時一緒に参加した方たちは優秀な方ばかりで、いまでは大学で教える立場になっていたりします。そこに混ぜてもらえたのは、大きな幸運でした」 とはいうものの、岩本さんのお話をうかがうと、社会の流れや変化に対し客観的な情報収集を怠らないという姿勢が伝わってくる。 子育てと翻訳と現在の岩本さんには母親という面もある。 「子どもが保育園にいる間が仕事の時間です。時間が限られているので、かえって集中して仕事しているかもしれないですね。以前なら夜中も仕事できたけど、いまはそうはいかない。とにかく、保育園に入園できてラッキーでした。そうでなければ、とてもきびしい状況だったと思います」 日常生活の中での切り替えの良さ、さらに仕事と家庭の両立にはスピードも必要なようだ。岩本さんの動作や話しかたからは、てきぱきとした方という印象を受ける。 「夫の協力も大きいですね。でも、息子がおままごとのときに『ぼく、お父さん!』と言って、エプロンをつけたときいたときは、さすがにショックでした。わたしもエプロンして、料理してるんですけど……。いまは小学校に行きはじめたらまた大変だときいているので、少し緊張しています。まあ、働く先輩ママも大勢いらっしゃるし、なんとかなるでしょう」 たよりになる編集者の理解と、岩本さんの切り替えの良さ仕事の速さで、ぜひ乗り越えてほしい。 最近の仕事 岩本さんの口からは謙虚な言葉が多く出てくるが、担当している編集者によると急ぎの仕事でも、しっかりとした原稿を仕上げてくれる翻訳者だという。 「『世界の果てのビートルズ』(2006年1月刊行予定)はスウェーデンの最北部で1959年に生まれたミカエル・ニエミが書いた自伝的小説です。その北の果てにビートルズのレコードがやってきて、少年たちの人生が大きく変わってゆく話です。当時、最新のロックを流していたラジオ・ルクセンブルクをきくためには、庭の木のあいだに銅線を張らなければならないような辺鄙な村の話ですが、訳しているあいだは、そこがまさにわたしの町でした」 ほかにもユーゴスラビア生まれでアメリカ在住の作家、アレクサンダル・ヘモンの全米批評家協会賞候補作『ノー・ホエアマン』も訳し、ギリシャ出身イギリス在住でウィットブレッド賞候補作家パノス・カルネジスのデビュー作も手がけている。英語圏以外の作家が英語で出版した作品の仕事が多くなってきた。 「ヘモンは渡米中にサラエボ包囲で母国に帰れなくなった作家で、英語が母国語でないからこそ、一語一語言葉を選び抜いた、非常に美しい英語を書きます。作品も細部まで作りこんでいるので、最後の最後まで新しい仕掛けを見つけては驚かされました」 この先はどんな本を訳していきたいのだろう。 「作品の心を伝えてみたいと感じたものなら、分野は選ばずやりたいですね。それにローリー・ムーアはぜひ。ムーアは言葉遊びの作家ととらえられることが多いのですが、翻訳で大事なのは、巧みなジョークをうまく訳すことより、そのジョークを言わざるをえなかった主人公の心の動きを伝えることなんですよね。『アメリカの鳥たち』にある短編にはムーアの30代が書かれているんです。訳していたとき、わたし自身もちょうど同じ年代に差し掛かり、目をそらして通り過ぎようとしていたことに向き合わざるをえなくて、かなりしんどい思いもしたのですが、小説を訳すってこういうことなんだっていう喜びもありました。ローリー・ムーアがこの先どんな作品を書くのかとても興味があります。もちろん、どんなものを訳しても発見があっておもしろいですね」 インタビュアー:藤野りえ(2005/11) |
